よいコーヒーとは友情のようなもの。豊かで熱く、そして濃い。
パンアメリカ・コーヒー振興会
珈琲を美味しく入れるには何が必要なのか。
UCCが言う珈琲の淹れ方の典型は次の通りである。
1,フィルタをセットしたドリッパに人数分の珈琲粉(グラニュー糖程度の中細挽き)を入れ、しっかりとならす。
2,お湯(温度は90度程度)を全体に馴染むように少し注ぐ。大体珈琲液がフィルタから滴ってくるのが目安。そこから30秒程蒸らす時間を置く。
3,蒸らした後、中心から、『の』の字を描くように注いでいく。
4,それを三回に分けて行う。一杯の量を120ccとするなら、40ccを三度と言った具合。
5,お湯を注ぐ際、フィルタにお湯を掛けないようにすること。
コーヒーを淹れる|おいしいコーヒーの淹れ方(https://www.ucc.co.jp/enjoy/brew/drip.html#beginner)
これが一般的に言われていることであろう。
しかし、これは飽くまで一例に過ぎない。これは美味しい珈琲の淹れ方と言うよりは、不味くならないような淹れ方という側面もあるだろう。
YouTubeなどにある動画などを見れば分かるだろう。珈琲の淹れ方はプロからアマまで千差万別で、最高に美味しい珈琲を淹れるに当たって、これと言うような淹れ方は無い。投げやりに言えば、最高に美味しい珈琲とは、淹れる人にとって美味しい物と言うべきだろう。
1,最も重要なのは、豆の質
いくら淹れ方を工夫したところで、豆の質が悪ければ、凡庸もしくは不味い珈琲しか出ない。
豆の質とは、最初に思い浮かぶのは鮮度というものだろう。
珈琲豆は焙煎し上がった直後から劣化が始まる。発生した炭酸ガスと共に、生成された香味成分がどんどん抜けていく。
それと、珈琲は湿気にも弱い。豆の焙煎過程で生成される苦み成分の一つ、クロロゲン酸ラクトンは、『酸』という文字から分かる通り、元々酸味成分だ。熱によって脱水縮合することで出来上がるわけだが、『脱水』によって生成されるということは、逆に言えば水分と接触すれば元に戻るということである。湿気のある所に豆を放置したり、或いは抽出して消費せずに放置した珈琲液がやけに酸っぱく感じられるのはこのためである。ちなみに、湿気による劣化の酸味が出る目安は、10日から15日程度である。
なお、酸化による酸味も発生することはあるが、こちらは湿気よりも遅い、大体一か月程度だ。大量に珈琲豆を買い込むでもなければ、あまり気にすることでもない。
2、豆は新鮮なほど良いとは限らない。
ここまで書くと、豆は新鮮なほど良いのか? と考えるだろうが、そうとも限らない。
焙煎後の豆には炭酸ガスが発生していて、さてはその炭酸ガスが味の抽出を阻害することがある。ついては、焙煎一日目二日目時点では、味の抽出が不十分になり、物足りなくなることがある。一般的には、48時間程度寝かせればガスが落ち着いて、そこから味が出るようになると言われている。
では一番美味しい時期はいつかとなるが、これも人によって変わるだろう。
例えば、珈琲界のAppleことBlue Bottole Coffeeでは、シングルオリジン(単一の農園による豆)であれば、6日目から8日目がベストとされている。そのため、Blue Bottole Coffeeの喫茶で出される珈琲はその辺りの豆が使われている。
が、豆の販売においては、敢えて焙煎から48時間以内の物を提供している。珈琲豆は炭酸ガスが落ち着いてから数日間は、どんどん味が出てきて美味しくなるということから、その変化を楽しんでほしいという方針であるらしい。
勿論これも、所詮は一つの意見に過ぎない。この他にも、四日目が一番美味しいなんて意見もある。何せ人の味の嗜好は十人十色。
中には、最初の二日間が一番良いと言う人さえ居る。焙煎したての豆は、炭酸ガスによって珈琲の味が薄まるものの、その代わり風味がよく感じられたりもする。珈琲の豆を注文されるお客様の中には、「苦くなくて酸っぱくなくて香りの良い物」というむちゃぶりをされる方もいるが、そういった方にはまさにこの飲み方が――豆の種類は置いておいて――最も適しているのではなかろうか。
3、豆の保存方法は出来れば冷蔵庫は避けたい。
ところで、豆の質を維持するために次に必要なことが、豆の保存の仕方である。
ここまで言った通り、焙煎した珈琲豆は高温多湿に弱い。だから、それを避けた所に入れるのが良いだろう。
例えば冷蔵庫。あそこであれば、冷たいし湿気も少ないし、日の光も当たらない。が、注意されたいことがいくつかある。
まず、冷蔵庫と室温の温度差。冷蔵庫で保存していた豆を取り出すとき、その温度差で豆に霜が付くことがある。これは中学の理科で習う飽和水蒸気量と言えば分かるだろう。これにより、豆が一気に湿気を吸い取るのである。
これの対策としては、気密性の容器に入れた状態で冷蔵庫から出し、十分に冷えを取ってから蓋を開けるか、一回の抽出で使う分を小分けにしておくというものがある。
それと、珈琲豆は多孔質と言って、炭と同じでスポンジみたいな構造になっている。つまり、匂いをよく吸い取るのだ。使い終わった珈琲粉を下駄箱の匂い取りに利用することだってある。この性質により、下手に冷蔵庫に入れておくと、他の食材の匂いを吸い取る恐れがある。ネギ風味の珈琲なんて飲みたくないだろう。
こちらの対策をするために、珈琲豆保存専用の冷蔵庫に入れておくという方法を取る喫茶店もあるそうだ。
以上のように、冷蔵庫で保存するには少々手間が要る。こちらで保存したほうが数ヶ月もつ利点はあるものの、二週間以内に消費しきれない豆を買い込んだでもない、或いは夏場で冷蔵庫以外に高温多湿を避けられる所が無いでもない限り、別の方法を取るのがベターだろう。冬場などであれば、エアコンの温かさのない無い廊下などを利用するという手が取れる。
その際に入れる容器は気密性が良い。密閉や密封ではない、気密性、である。要は、内部の空気圧を高めて豆からガスや香味成分が抜けるのを防止するのである。専用の容器が無いのであれば、炭酸飲料のペットボトルに入れておけば、豆自身から発生した炭酸ガスにより内部気圧が上昇し、気密状態になる。そう言えば、コーヒーハンターこと川島世彰氏が珈琲を抽出している動画では、ワインボトルらしき物の中に豆を保存していて、コルクを抜く際に、ポンッと小気味良い音が響いた。斯様な音を楽しむのも、また一興ではなかろうか。
4,焙煎したての豆が欲しい場合
あとそれと、珈琲豆の鮮度を管理するにあたって、焙煎日が分かるほうが良いとのことで、注文してから焙煎して提供してくれる店に行こうと考える方へ、一つ留意していただきたいことがある。
豆を焙煎する際に、回転するドラムにコンロやバーナを当てる所謂直火式焙煎をするところの場合、大分時間が掛かることがある。コンロの火力にも依るだろうが、参考に、カセットコンロで200gを焙煎する時間は、15分~20分程は掛かる。このような店を利用する場合、店の駐車場のキャパシティの問題や、時間が無い人には向かないかもしれない。
ジェットロースタと呼ばれる、半流動式の焙煎機であれば、超高温でさっと焼いて提供できる。200gであれば、豆を冷却する時間合わせて5分も掛からない。その代わり、含有している水分を抜く時間が無いため、物によっては青臭い味が出るかもわからない。どちらを選ぶかは、利用する人次第であろう。
終わりに
以上、今回は、珈琲を美味しく淹れるための知識の一部を紹介した。今後ここでは、美味しい珈琲を淹れる方法を各々が追求できるように、本やネットや動画サイトなどで知った知識を掲載していくことにする。
次回は、ペーパドリップによる抽出方法の工夫について、語ろうと思う。
〈参考文献〉
・旦部幸博(2016). 『コーヒーの科学 「おいしさ」はどこで生まれるのか』. 講談社.
杉山世子. “焙煎後48時間の真実”. 豆乃木. 2015-02-09. https://www.hagukumuhito.net/news/?mode=detail&article=242,(参照:2022-08-13)

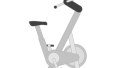
コメント